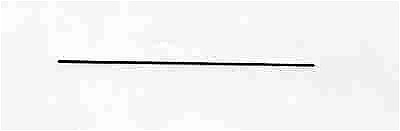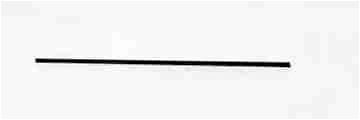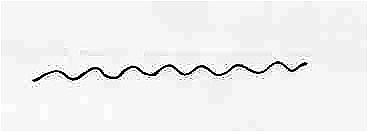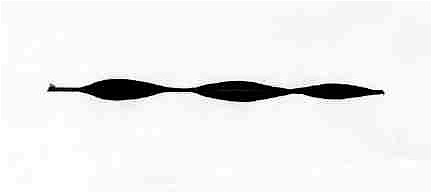夏目房之介は、<線>の不思議な性質を、機能的・記号的に見すぎて、「迷 路」に入っているように見える。つまり、<線>の性質のひとつである、機能 的・記号的な側面を拡張し過ぎてしまっていると、僕には思われる。 ここでもう一度、藤子・F・不二雄の素朴な疑問に立ち返ってみることにす る。
ようとしてもできるもんじゃない。文字通りモヤモヤしてモウモウと して取りとめないのです。それを、まんがは何本かの円弧か、短い斜 線の組み合わせでとにもかくにも表現するのです。 風も不思議です。空中に何本かの線を浮かべて、それが風に見える のです。大きな音、驚き、物の動き、すべて簡単な線で表され、読者 も何の抵抗もなく受け入れています。実に不思議です。 何よりも不思議なのが輪郭です。一本の線でグルッと囲っただけで、 その中の空間が、顔になり、外の空間は、外界になる。これはまんが に限りません。洞窟に残された古代の壁画。長方形に区切られた空間 は、角と四肢を意味する六本の単線をともなうことで牛を表します。 牛を描こうとした古代の画家の意志は、何万年もの歳月を隔てた僕等 にも確かに伝わってくるのです。
藤子・F・不二雄の言うように、<線>とは、マンガに代表されるように、い くつかの<線>を組み合わせることによって、記号的に、いろいろな事物の形を 切り取ったり、目に見えない風や雲のような自然現象を描くことができたり、輪 郭線を引いて、<内と外>などの、次元の違いを表現することができるものだ。 これらの要素を総合して、今、この性質を、<線>の輪郭(記号)性 と呼んでおくことにする。 しかし、まだこれは、単に<線>の一側面を表しているにすぎない。ここを拡 張し過ぎてしまうと、<線>の本質にたどりつけないのだ。 ところで、僕には<線>について、もうひとつ不思議に感じられることがあ る。 それは、「<線>には、感性的な手ざわりみたいな要素がある。」とい うことだ。一言に<線>と言っても、太さや、タッチによって、僕たち見る側 に、いろんな感じ(感覚の手ざわり)を、あたえる。これも、とても不思議な ことなのだ。 たとえば、
これは、定規で引いた普通の線だ。一般的に、マンガのコマやフキダシを描く ときによく使われている。機能的で、シャープな感じを受ける。たとえば、これ を極限まで押し進めたのが、大友克洋の<線>の印象だ。 この線を、もう少し太くすると、こんな感じになる。
僕にはこの線は、前の細い線よりも、力強い感じに見える。線の太さが変わる と、受ける印象が違ってくることがわかる。これは、いわば、劇画の<線>の 印象にあたっている。 また、同じ線でも、フリーハンドで描くと、こんな感じになる。
これだと、同じ細い線でも、機能的な感じではなく、やわらかくて、あたたか い、人間的な感じがあたえられる。この典型は、手塚治虫の<線>の印象があ げられる。 つまり、初期のマンガの<線>は、ほとんどこんな感じだったわけだ。 また、同じように、手で描いても、
これだけグニャグニャになると、やわらかすぎて、とても不安定な印象を受け るようになる。僕には、滝田ゆうの<線>の印象が、すぐに思い出される。ほ かにも「ヘタウマ」と言われているマンガの<線>は、こんな感じだ。 まだ、あるのだ。
これは、一本の線の太さに、強弱をつけた場合だ。 どういう印象を受けるかと言うと、<立体感>が出た感じになる。太いとこ ろは立体性の強い部分を表し、細いところは立体性の弱い部分を表している。こ の<線>を使うことで、たとえば、人間の身体の輪郭の、微妙なでこぼこの立体 感を、表現することができる。この<線>の使い方で、最近一番印象深かったの は、あだち充の女の子を描く<線>だ。また、永井豪の裸の女の子の画像など は、典型的にそうだ。身体の膨らんで、丸い部分を、<線>を太くすることで、 とてもうまく表現している。 このように、同じ線であっても、太いか、細いか、ペンで描くか、筆で 描くか、直線的か、曲線的か、定規を使うか、フリーハンドで描くか、 タッチの強さ、弱さの微妙な違い、などよって、受ける印象がまったく 違ってくる。 これは、どういうことなのだろうか? ある<線>からは、やわらかなあたたかい感じを受けたり、ある<線>から は、機能的でシャープな感じを受けたりする。またある<線>からは、不安定な 感じを受けたり、ある<線>からは、立体的な感じをうけたりする。 もちろん、同じことは、マンガ家にも言える。ある作家の<線>からは、 冷たいクールな感じを受けるし、ある作家の<線>からは、あたたかい感じを受 ける。また、ある作家の<線>からは、粗雑な感じを受けるし、ある作家の<線 >からは、繊細な感じを受ける・・・・・・などだ。 これらの<線>の感じが、それぞれの作家の特徴(個性)になってい るし、読者も、無意識(あるいは、意識的に)の選択で、その<線>の 感じから、作家の好き嫌いを決めたりしている。 たとえば、風の表現にしても、数本の線分だけで、風を、記号的に表現するこ とができる。確かに、それで、「風が吹いている」と理解できるのも不思議なこ となのだが、僕の感じでは、このとき同時に、さわやかな風の<感じ> や、激しい風の<感じ>なども、感じ取っているはずなのだ。 だから、<線>は、どこかで、<現在までの人間の感性の累積の手ざ わり>に触れることができているもののはずだ。そうでなければ、こんな ことがあり得るはずがない、と僕には思える。 これらの要素を総合して、今、<線>の感覚(の手ざわり)性と呼ん でおくことにする。 今まで見てきたところで言えば、一本の<線>は、一方では、輪郭線に象 徴されるように、現実のものを描写する切り取る記号的な側面(<線> の輪郭(記号)性)を持ちながら、同時に、もう一方では、人間にいろ んな感覚の手ざわりを抱かせる感性的な側面(<線>の感覚(の手ざわ り)性)を持っているものだ。 これを、僕はここで、<線>の二重性と、呼ぶことにする。 僕の感じで言えば、<線>は、直線的になるほど、感性的な度合いが弱くな り、輪郭性の度合いは強くなる。反対に、<線>がグニャグニャになるほど、輪 郭性の度合いは弱くなり、感性的な度合いは、強くなる。 また、<線>は、太くなるほど、輪郭性は強くなり、感覚性は弱くなる。反対 に、<線>が細くなるほど、輪郭性は弱くなり、感覚性は強くなる。 つまり、一般的には、<線>というものは、太くて、直線的なほど、 輪郭(記号)性は強くなり、感覚(の手ざわり)性は、弱くなる。反対 に、細くて、曲線的なほど、感覚(の手ざわり)性は強くなり、輪郭 (記号)性は弱くなる、と考えられる。 これを図にすれば、次のようになる。 <線>の二重性の振幅 こういう表し方をすると、<線>には単純な組み合わせしかないように思われ るかも知れないが、実際には、太くて曲線的な線や、細くて直線的な線もありえ るし、線の太さ細さは、微妙に変えることができるし、グニャグニャの線にして も、曲がり具合いは、微妙に違えることができるわけだから、この<線>の組み 合わせのバリエーションは、描く人の数だけ、ほとんど無限に存在するはずだ。 マンガ家の数だけ、マンガの線のタッチがありえるはずだ。 |