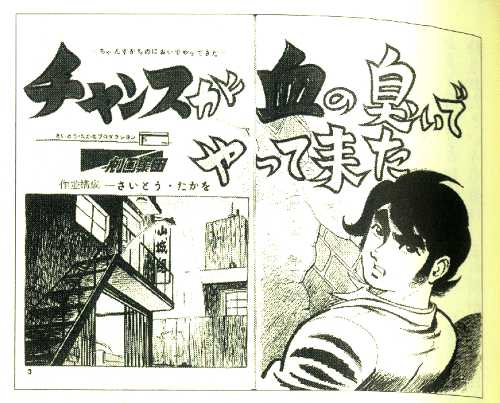『貸本マンガ史研究』という本があるのをはじめて知った。 その中で、さいとう・たかをの評価が、とても低いことに驚いた。確かに、そう考えて みると、「劇画」の誕生が語られる際に、辰巳ヨシヒロ、佐藤まさあき、などが中心的に 取り上げられる(確かに、中心なわけだが)が、さいとう・たかをは、あまり取り上げら れていないように見える。 さいとう・たかをは単純にカッコイイ絵で、軽い皮肉なお話を作ったにすぎ ないのだろう。おおむねさいとう・たかをの作品はこれと似たようなものばか りである。内容的になにかきわだったものがあるわけではない。さいとう・た かをの作品批判がここでは目的ではない。読者がどのようにさいとう・たかを の作品を受け入れ、どう反応したかが問題なのである。だが、読者の投稿文を いくら読んでも、なにも見えてこないのだ。 そうではないのではないか、と僕には思える。 この評価は、逆になるべきではないだろうか。 さいとう・たかをが、「単純にカッコイイ」内容の作品を描く、それに見合った <線>を実現したことが、画期的なことなのだ。 手塚治虫の丸くてやわらかなタッチの<線>を否定して、劇画のタッチや内容として、 辰巳ヨシヒロや佐藤まさあきは作品を描いた。初期の劇画の基本的なスタンスを確立した 功績は大きいと言える。 だが、<線>の問題として言えば、スッキリとした劇画タッチの<線>を開発したの は、さいとう・たかをだったと言える。その功績もまた、ちゃんと評価されてしかるべ きだと思う。 手塚治虫が、日本的な独自のストーリーマンガの<線>を開拓したように、さいとう・ たかをは、日本的な劇画の<線>を開拓した最初の人だと言えるのではないだろうか。 当時のさいとう・たかをの<線>の画期性について、池上遼一は、こう語っている。 −中学生にとってはさいとうさんは力があったわけですね。 池上 マンガ家になりたくてもんもんとしていた少年に、そういうバイタリテ ィーをあたえてくれたという意味ではね。ある意味ではマンガ界のプレスリー みたいなものだよね、新しい音楽を開拓したというか。この人が手塚マンガか ら脱却して平田さんとおなじように、リアルな絵柄を開拓したということだよ ね。ただ、平田さんのは一般受けするリアリティーじゃなかった気もするけど ね。… ○ 池上 だれもが描いていない線というか、走る線にしてもシャープというか都 会的というか。手塚さんから脱却してるというか。アメコミのあのどろくさい 陰影でもなくて、日本人に合うなという気がしましたよね。 −辰巳さんの作品はどうでした。 池上 好きでした。さいとうさんに近い感じで好きだったんです。Gペン使っ て。それまではたぶん、手塚さん的な絵はカブラペンだったと思うんですよ、 強弱のない。それが、さいとうさんになって強弱のある線になった。厚みがあ るというか。あの当時の劇画工房の人たちはみんなGペンじゃないですか。あ れに妙なリアリティを感じたんじゃないかな。かっこいいなというか。アクシ ョンの線にしても、それまでの手塚さんのきちんとした線じゃなくてがさつな んだけど、すごくリアルな感じがしました。 あの当時映画的手法をすごく取り入れてたんじゃないですか、劇画は。手塚 さんだったら、クルマが走りながらひとつのコマにいっぱいセリフが入ってい る。そんなことありえないじゃないというね。それが劇画では、クルマの中が 描写されて人物の周りにふきだしがあるとか。あとは、時間かな。手塚さんの は、1ページのなかにごちゃごちゃセリフがあって、あまり読むスピード感を 計算してないところがあったでしょ。ところが、貸本の劇画は読むスピード感 を計算してたっていうかね。そういうのが魅力だったんじゃないですかね。松 本さんにしてもサイレントのコマがあったりして、あの当時けっこう映画的な ものをとりいれてたのかなあと思いますよね。 さいとう・たかをが、どこから自分の<線>を獲得してきたのか、それはよくわからな い。ただ、さいとう・たかをは、マンガにとって、<線>が、とても重要なものだ、とい うことにかなり自覚的だったのではないだろうか。 「劇画家にとって自分の絵というのは重要な要素である。確かに、構成などの いろいろな要素が加わるのだが、とりわけ絵のタッチ、つまり『線』は重要な 表現要素になる。」 「とにかく私はリアルなドラマをリアルな絵で表現したいと思っていた。もち ろん、私自身もそういった時代の潮流に乗ったような絵を描いてはいたが、そ こから早く脱皮して私のオリジナリティーを確立したいと考えていた。ところ が、物語のほうはある程度リアリティーに富んだものができるのだが、絵のほ うがどうも思い通りに描けない。物語と絵のズレはどんどん開く一方だった。 どうにかしてもっと物語に合ったタッチの絵を描こうとずいぶん試行錯誤した。 (略)しかし納得できる絵にはなかなか到達できなかった。」 「(略)そして、ついに自分で一番嫌いだった線の細さを感じさせない力強い 絵に行き着いたのだ。それが昭和三十三年の『台風五郎』である。絵に悩み始 めてから一年あまりをついやしていた。今の絵の原点は、この台風五郎にある と言える。そこからゴルゴ13も無用ノ介も生まれたといっても過言ではないだ ろう。」 このさいとう・たかをの発言は、僕には妥当なものだと思える。
さいとう・たかをの<線>は、タッチとしては、アメコミなどの劇画の、輪郭性の度 合いの強い<線>の影響を受けているように見える。 しかし、さいとう・たかをは、それを、日本人の感覚に見合うように、独特の<線>に 変換することに成功した。 さいとう・たかをによって、劇画の<線>の水準が高められたことは疑いを入れないと 思う。もっと妥当な評価をされてしかるべき人だ。 劇画の<線>の拡張ということで、もうひとり、触れておきたい人がいる。 ありかわ栄一だ。 さいとう・たかをの開発した<線>の影響を受けながら、この人は、劇画の<線>に おける効果線の部分を、飛躍的に拡張した人として、もっと評価されていいと思え る。
効果線は、それ以前まで、フリーハンドで描かれていたらしい。 ありかわ栄一は、その部分を、くも形定規や、コンパスなどをつかって、アクションシ ーンを描いた。それは、「効果線」の決定的な飛躍を意味していた。特に、初期の劇画 は、「動き」を表現することが多かったので、それ以降に与えた影響は大きかったと思 う。この効果線が、現在では、普通の表現になっていることが、それを証明している。 技法には特許がないので、「いい」と思えば、みんながマネをするようになるのだ。 ありかわ栄一の『アイアンマッスル』は、ストーリーは単純だが、画像もきれいで、フ キダシの形も、効果音も、視覚的で、緻密な画面構成によって、一枚の絵のように描くこ とができている作品だ。定規やコンパスによる効果線は、抜群で、様式美のようにまでな っている。 (この項、了) |